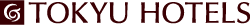その気候帯は、南イタリアからシャンパーニュまで
- 北アルプスを望む信州・高山村。
「信州たかやまワイナリー」のモダンな建物。いま立っているのが、標高650メートル。
空に向かって伸びているようにも思える畑は、高いところで830メートル、低いところで400メートル。一面を眺めていると、ここがかつて遊休荒廃地だった土地とはとても思えない。
400メートル以上もの標高差は、ひとつの村にヨーロッパの気候帯を凝縮したかのような豊かな幅をもたらす。南イタリアの陽光、ドイツの涼やかさ、そしてシャンパーニュの繊細さ──それらがすべてここにあるような、不思議なバランスで重なり合っている。
「ですから、同じ品種の葡萄でも、畑の位置によって収穫期が2か月ずれることもあるんです」
醸造家・鷹野永一さんは、もう30年もワインとともに生きている。 
-
畑は40区画以上。ワイナリーの代表・涌井一秋さんをはじめ、多彩な個性を持つ13人の栽培家たちがこの土地の代表品種・シャルドネをはじめ、メルロー、ピノ・ノワール、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨンなどと向き合っている。区画ごとに品種も条件も異なる畑で、それぞれの人がそれぞれのやり方で手入れをし、育て、豊かな収穫を目指す。
「育てる人の素養が葡萄に出るように思えます。陽気で賑やかな人が手掛ければ、その葡萄はどこか華やぎをまとい、穏やかで物静かな人が向き合えば、落ち着いた奥行きを感じさせる葡萄になります。ただし、葡萄の出来を人が評価するのは、お天道様を評価しているようなものですから、ワインづくりは、やはり自然にゆだねることから始まります」
収穫期になると、畑ごとに成熟度合いを測って、適熟期に収穫された葡萄が、ほぼ毎日、次々に醸造所に運ばれてくる。多彩な個性を持つ栽培家が育て上げたそれぞれの葡萄を、鷹野さんが「高山のワイン」に仕込む。
「このワイナリーのキーワードは、“多様性”です。立地、品種だけでなく、携わる人やワインづくりそのものも……」
長野県が進める「信州ワインバレー構想」の5つのエリアのひとつ、「千曲川ワインバレー」のなかでも、高山村はとりわけこの“多様性”を象徴する産地とされている。 
仕込みの哲学と、偶然がもたらす贈りもの
- 除梗・破砕(※1)を経た葡萄はプレス機へ送られる。ここで採用されているのは「グラヴィティ・フロー」。果汁が重力に従って自然に移動するため、余計な圧力がかからず、雑味を出さない。
「特に赤ワインに有効です。皮も種も一緒に漬け込みますから、いいものばかりでなく余計な成分も出てしまう。どこまで漬け込むか、そのタイミングの見極めとともに、その後の工程でも注意が必要ですね」
醸造家の腕の見せどころだ。
だが、ワインづくりの大半を占めるのは、実は華やかに思える仕込みではないと鷹野さんは言う。
「ワインに水は一滴も入っていませんが、私たちの仕事の7〜8割は、水を使った容器や器具の洗浄です。つまり衛生管理ですね」
排水処理や作業場の清浄を徹底することが、健全な発酵や育成を守る第一歩。
発酵を終えると、冬の寒さが厳しい高山村ではステンレスタンクの特性を活かし、低温安定性を確保することで、異物と誤認されやすい“酒石(しゅせき)”の析出を防ぐ。樽貯蔵や瓶詰めの段階でも、15℃以下に設定できるような能力のあるエアコンで、微生物の繁殖を防ぎ健全に育成する環境を整えている。
「アルコール発酵を担うのは酵母ですが、これは自然界から人間が選抜したものです」と鷹野さん。
「ただし、人間に選抜されていない微生物はどこにでもいますから、その動きをできるだけ抑えたいんです」 
- ワインはタンクだけでなく樽にも移される。だが、「この樽が正解」という決めつけはしていないのだとか。
「ワインと樽の相性も一期一会。このワインにはこの樽だと決めつけず、そのとき空いている樽に仕込んでみて、必ず検証する。そうやって繰り返すなかで、感覚が磨かれていきます」
鷹野さんはそう語りながら、「けれど、人間の思考がすべて正しいわけではありません」と笑う。思いもよらない偶然の調和を生むのもまた、ワインの世界だ。
「ワインは、たまに大きなプレゼントをくれます。想像もしなかった香りや味わいに出逢えることがある。その瞬間のために、私はワインをつくり続けているのかもしれません」
初めて自分でつくったワインを口にしたときは、感動どころか落胆すら覚えたという。数か月後、1本のワインを上司が笑顔で差し出してきた。そのグラスの香りと味わいに唸らされ、それが自分のワインだと知ったとき、驚きと喜びが押し寄せた。それ以来、鷹野さんはセレンディピティ、つまり「偶然がもたらす幸運」を信じ、追い求めている。
「それは、ただ待っていてもやってこないんです。アンテナを張り巡らせ、チャンスだと感じたら躊躇することなく飛びつく。すると幸運の種が芽吹いてくると考えています」
※1除梗・破砕(じょこう・はさい):葡萄の房から茎を取り除き、その後葡萄の粒を軽く潰すこと。 
高山村の象徴、フィールドブレンド
- 「信州たかやまワイナリー」のワインは、大きく3つのラインに分けられる。
品種ごとの個性を前面に押し出したワイナリーの主力、「ヴァラエタルシリーズ」。地域限定で楽しめる白・ロゼ・赤の「ファミリーリザーブ」。さらに「ラボシリーズ」は、試験的に仕込む“小さな挑戦”で、製造の継続を前提とせず、その時々の発想で瓶詰めされる遊び心あふれるラインだ。いずれも目指しているのは、「食事とともに、ずっと飲み続けられる」こと。強烈な個性の一杯で満足させるのではなく、日本の繊細な食文化に寄り添う、バランスの良い味わいを目指している。
そして、このワイナリーを象徴するのが「ラボシリーズ」の1本、混醸の「たかやまフィールドブレンド」だ。ブレンドワインづくりは、品種が異なれば生育度合いも異なるため、品種ごとに収穫・仕込みを行い、必要に応じてワインになった後にアサンブラージュ(※2)するのが一般的だが、このワインは、収穫した複数の品種を同じタンクに入れ、その泡立ちのなかで互いの個性を重ね合わせて成長させていく。
「村全体をひとつの畑に見立て、畑で隣り合って育ったものを醸造所で一緒に仕込む。自然の流れに沿ったこのやり方もまた、素直においしいワインになります。多様なものが集まれば、そこには必ず調和が生まれるんですね」
すでに、販売された製品のうち、村内各地の畑から集められた2022年の白葡萄で、芳醇さの高かった品種を一緒に醸造した「STW124 たかやまフィールドブレンドアロマ系混醸(白)2022」(生産本数344本)の1本を開けてみた。 グラスに注ぐと、やわらかで黄桃のような甘い果実を思わせる香りが垂直に立ちのぼる。口に含むと柑橘系の爽やかな酸がきりりと広がって軽快。少し時間が経過すると、かすかなビターの余韻が感じられるようになって、でも透明感が増していくのが不思議だ。
ひとつの輪郭に収まらないワイン。これが、いくつもの品種が一緒に仕込まれたことで生まれる複雑さ?
それは、高山村、そして「信州たかやまワイナリー」の姿に重なる。
標高差と気候の変化、人々の個性、最新の技術、そして偶然の調和。そのすべてが、このワインに結びつく。
「テロワールは環境だけでなく、人の営みや、偶然の出来事までをも含む、と私は思っているんです」
グラスのなかに、異なるトーンが幾重にも響き合う。その調和が生む香りと味わいが「高山色」を映し出す。
※2:アッサンブラージュ:元は美術用語で、「組み立てる」「積み上げる」などの意味で、ブレンドワインをつくる際の「調合」などの際に使う。
東急グループ・オリジナルワイン
瑠璃のしらべ Takayama Blanc 2023
- 東急百貨店、ながの東急百貨店、東急ストア、東急ホテルズのソムリエたちが「東急グループのソムリエの力を結集したオリジナルワインをつくりたい」という思いを込めてプロデュースした「瑠璃のしらべ Takayama Blanc 2023」は、複数の品種を一度に収穫し、同じタンクで仕込んだ混醸の白ワイン。畑の多様性がグラスに映し出される一品だ。この秋、ザ・キャピトルホテル 東急、横浜ベイホテル東急、渋谷エクセルホテル東急、羽田エクセルホテル東急で提供予定。また東急百貨店、東急ストアの一部店舗で販売予定。

信州たかやまワイナリー
SHINSHU TAKAYAMA WINERY
- 住所:長野県上高井郡高山村大字高井字裏原7926
TEL:026-214-8726
営業時間:9:00〜16:00
(close12:00〜13:00)
定休日:年末年始
アクセス:・上信越自動車道〈須坂長野東IC〉から車で約25分
・長電バス「役場前」から徒歩約20分
www.shinshu-takayama.wine 
- 今回の取材先はいかがでしたか?
信州・長野での旅行を楽しんでいただけることを願っています。
comforts.jpは、東急ホテルズが運営する、旅行好きの皆様に向けたウェブメディアです。
日本の魅力的な観光地やその土地の美味しいグルメ、文化や最新のトレンドなど、好奇心を刺激する旅行情報を厳選してお届けしています。
さらに、ホテルでの過ごし方や周辺の散策スポットなど、旅をより豊かにするヒントも多数ご紹介。
旅行へのワクワク感を高め、思い出を輝かせるパートナーであるために、comforts.jpは、もっと楽しく過ごせる、多彩な旅行情報をお届けします。