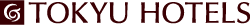- 5歳からダンサーのキャリアをスタートし、俳優としても映画『世界の中心で、愛を叫ぶ』(04年)で大ブレイク。以後、映画やドラマ、そして舞台でも大活躍の森山未來さん。2013年にはコンテンポラリーダンスの第一人者が主催するイスラエルの<インバル・ピント&アブシャロム・ポラックカンパニー>に1年間留学。その磨き抜かれた<技>は、2021年7月に開催された東京五輪開会式で披露され、荘厳にして圧倒的なダンス・パフォーマンスに絶賛の声が相次いだ。
- そんなマルチな表現者として稀有な道を歩み続ける森山未來さんの新作映画は『ボクたちはみんな大人になれなかった』。原作はウェブ連載中から話題となった作家・燃え殻による半自伝的恋愛小説。コロナ禍の2020年からバブル崩壊の1990年代半ばまで遡る抒情詩的な作品との出会いや、主人公を演じて見える“いま”についてうかがった。
- 「最近、自分がフィクションの小説を読むことがなくなって、何かしらの研究書とか、エッセイばかりを読んでいるのですが、同時に、恋愛映画にもう一度タッチしてみたいという感覚が芽生えていました。そんな中でこの作品のオフ ァーをいただいいたので、純粋に乗ってみたいなと。もうひとつ背中を押したのは、この原作がベストセラーになっているということ。もちろん、その時々で求められる本、流行る本というのはあるのですが、いまの流れの中で、この本がポン!と飛び出してきたことには必ず意味がある。そういうものにタッチしてみたいという感覚がありました」
- 演じてみて、「ポン!と飛び出した」理由は、おわかりになりましたか?
- 「この本って多くの人々に“エモい”と称されていますが、その“エモい”という言葉が現在流行っている理由が、絶対にあると思うんです。“そんな薄っぺらい言葉を使って”みたいなことは簡単に言えますが、やはり言葉として流通していること自体に大きな意味がある。同じように、スピリチュアルなものを“スピ系”と称するみたいな。僕自身は、“エモい”も“スピ系”も大嫌いですけど(笑)。でも、やはりそれぞれの言葉が流行っているということは無視できない。いまを生きている人々の心を映すというか……。たとえばスピ系が流行るのは、みんな精神的なことを素直に話せなくなっているからだろうと思うんです。例えば、昔の人が“お天道さん、大事にしなあかんよ。お天道さんに怒られるよ”みたいに言っていたようなことが、ナチュラルに受け入れられた時代といまは違うのかもしれない。極端に言うと、“なんで太陽に怒られるのか?”ということが科学で立証されなければならない、みたいな。となるとスピリチュアルな話をすることがものすごくはばかられる。“エモい”も同じで、例えば、SNSの普及で全ての人が情報を発信できるようになった反面、監視社会的な側面も強くなった。だからこそエモーショナル、つまり感情的、情緒的な表現をすることが難しくなったとも考えられますよね。エモーショナルな感情に飢えているからこそ、こういう言葉が流行るのだろう、そしてこの本がベストセラーになったのだろうと、勝手に解釈しています」
- 主人公は、テレビの美術制作会社で働く46歳。ふとしたことから初恋を思い出し、過去に思いを馳せる。現在37歳の森山さんだが、スクリーンの中では20代も40代も違和感がない。
- 「いまはプチ整形も手軽にする時代になって、美容系の技術も発達している。今回は、そういうことを積極的にやってみました。ヒアルロン酸を入れるとか、石膏パック、シートマスク、美容マッサージ、美容鍼も。とにかく勧められたものはすべて試して(笑)。もちろん、どうしても絵的に必要なところは、合成も少し使ってリアリティを出して。でも、結局、大事なのは老けたとか若返ったというところに観ている方の目がいかないようにすること。外見より、その人の人間模様がどのように移ろっていくかを伝えるほうが大事でした」
- 内面的な役作りですか?
- 「役作りというか……。まず単純に生まれた環境は選べないでしょ。若い頃はその限定された対人関係がすべてであり、その狭い世界で生きている。それは人によっては鬱屈とも呼べるかもしれないけれど。次第に新しい環境に身を置くことになり、いままでの視野が良いか悪いではなくて、とにかく破壊されていく。女性も含めて出会う人も変われば、仕事場での自分の立ち位置も変化して、いろいろなものとの関わり方が変わってくる。その変容によって生まれる振る舞いとか、人に対しての距離感。そういうものを意識していました」

©2021 C&I entertainment
- 1990年代半ば。主人公が文通相手かおりと初めて待ち合わせをするのが原宿ラフォーレ前。二人の初恋を育む街が渋谷。タワーレコード、シネマライズ、衣料雑貨店・元祖仲屋むげん堂、そして円山町のラブホテル……。当時、サブカルチャーのメッカとして若者が憧れた街の空気感がノスタルジーをかきたてる。
- 「原宿や渋谷、通っていました。11歳の頃。1996年ごろに、舞台稽古のために母親と上京して。その時に母親が原宿の<ブラームスの小径>にある木造の民家みたいなお抹茶屋さんを見つけて、そこによく行きました。
じつは、かおりと初デートをするのがまさにその周辺だったので、僕自身、当時の原宿を思い出さずにはいられなかったというか。ノストラダムスの予言が外れたころの99年も、渋谷のパルコ劇場で上演された『BOYSTIME』のミレニアムカウントダウン公演が初日で、その稽古のために、円山町にあるマンスリーマンションに2ヶ月くらい滞在していました。だから、主人公と同じ境遇ではないし、年齢も違う。でも、あの時代の東京に僕もちゃんと居たという……。そのへんのシンクロが、僕をややこしくさせて困ったんですよ」

©2021 C&I entertainment
- 感情移入しすぎて、演じにくかったとか?
- 「これだけ過去を引きずる主人公はもちろんセンチメンタルで、映画の描かれ方もノスタルジックにならざるを得ない。だからこそ“エモい”につながるんでしょうけど。だけど、エモいものをエモく表現すると臭くなるから、僕としてはできるだけ淡々と演じたかった。でも僕自身の実際の記憶と混ざってくる部分があって、気持ちが引っ張られてしまった。さらに、2ヶ月という短い撮影期間の中で、過去に行ったり現在に戻ったり。過去を回想している25年後の主人公と、過去を体験している主人公と僕自身の記憶との距離が近すぎて、全てがぐちゃぐちゃになってしまった(笑)。結局、まんまとノスタルジックな渦に飲み込まれてしまった感じがするんですよ」
- その“混沌”は、役作りに貢献したのでは?
- 「まぁ、良かったんじゃないですか。いや、ということは森(義仁)監督の手のひらで踊らされていたってこと?そうは思いたくないなぁ(笑)。そういえば、最近はこういったタイムリープ(時間移動)の映画がよくあるじゃないですか。クリストファー・ノーラン監督の『TENETテネット』とか、日本だと新海誠監督の『君の名は』とか。僕としては撮影前に、“最近はこういう手法はあるあるなので多用は避けましょう”と監督に提案したのですが、“任せてください”と言われつつ、まんまとタイムリープして(笑)。まぁ、完成した作品を見て、もちろん自分が出ている作品を客観的に観て良し悪しはなかなか判断できないのですが、でもギミックとしての面白さはあるなと思っちゃいました。これまた、監督にしてやられたってことですかねぇ(笑)」
- 文通で知り合い、公衆電話で連絡をとってデートを重ねた初恋の人。別れて以来、20年以上も会うこともなかった彼女の消息を知ったのがSNS。本作には、文通に始まるコミュニケーションツールの進化も描かれている。
- 「その変容を全部、意図的に見せていますよね。逆に、“人と繋がりたいということの切実さ”は変容していないということが浮き彫りになる。文通やピッチだったら、手紙が返送されなくなる、あるいは“おかけになった電話番号は現在使われていません”となれば、そこからつながる術がない。それが当たり前で、それが人との距離だった。だからこそ、会えたときの熱量はすごく高かったはず。別れてしまったら、会えない、追えない……。そりゃ、今の僕たちからするとエモいってなるよなと。コミュニケーションツールは便利になったけれど、感情の振り幅が狭くなっている。かつての驚きと感動を、いまの人たちは欲しているのかもしれませんね」
- 主人公の過去への旅は、ふと目にしたかおりのSNSから始まる。まるでパンドラの箱を開けてしまったかのように。そんなご経験は?
- 「ちょっとあったかなぁ(笑)。携帯電話を持っていなくて、PCは持ってるけど街なかで気軽には開けない。だから“夕方に渋谷周辺で”なんていうユルイ待ち合わせをされると困る(笑)。“何時にハチ公前”とか決めてくれないと、絶対に会えないですから。でも、携帯電話を持つことが当たり前じゃない世界で生きていると、誰かとばったり出会ったときの感動はひとしおですよ」
- タイトルから最初に浮かぶのは「大人ってなに?」という疑問ですが。
- 「それを考えてた時に思い出したのが、中高生ぐらいの時に読んだ『うしおととら』という漫画です。主人公は嘘のつけない少年。彼が、飛行機事故で視力を失った男の子に、父親はその事故で死んだと告げられなくて、さりとて生きているという嘘もつけなくて、すごく苦しむ。そして最後に男の子を傷つけないための嘘をつく。それを読んだ時、嘘をつくことの意味、人を傷つけないための嘘というものを考えました。単純な考えかも知れませんが、人の思いを背負いながら嘘をつくのが大人だとするなら、大人になるのも悪くないなと、思ったりもします。この映画のタイトルを見た時の”大人"という言葉に対する反応は人それぞれだと思いますが、主人公がどういうふうに生きてきたかを観ながら、”大人とは何か”を改めて一緒に考えて欲しいと思っています。僕は、そんなにネガティブに受け止めてはいません」
MIRAI MORIYAMA
- 1984年兵庫県生まれ。5歳から多様なジャンルのダンスを学び15歳で本格的な舞台デビュー。2004年には映画『世界の中心で、愛を叫ぶ』で、日本アカデミー賞新人俳優賞ほか多くの賞を受賞。2013年には、文化庁文化交流として、イスラエルのテルアビブに1年間滞在し、インバル・ピント&アヴシャロム・ポラックダンスカンパニーを拠点にヨーロッパ諸国にて活動。主な映画出演作に、『怒り』(16)、『アンダードッグ』(20)などがあり、2019年にはNHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』にも出演。
『ボクたちはみんな大人になれなかった』
- 1995年、ボクは自分より好きな人に出会った。“普通”が嫌いな彼女に認められたくて、映像業界の末端でがむしゃらに働いたけれど、ある日、彼女はふと姿を消した。そして2020年のいま、ボクは駆け抜けてきた過去に思いを馳せる……。バブル崩壊の90年代からコロナ禍の現在までを時代を彩るカルチャーとともに綴った、ベストセラー恋愛小説、待望の映画化。
- 監督:森義仁脚本:高田亮原作:燃え殻
出演:森山未來、伊藤沙莉、萩原聖人、大島優子、東出昌大、SUMIRE、篠原篤 - 11月5日(金)より、シネマート新宿、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほかで上映&NETFLIX全世界配信開始
-
bokutachiha.jp
※Webサイトで最新情報をご確認の上、お出かけください。