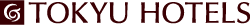アトリエ・ド・フロマージュ
“日本のブルゴーニュ”で味わう、宝石のようなチーズたち
- 清らかな空気、山から吹き下ろす風、そして湯の丸高原の水。
発酵に理想的な環境に恵まれた東御の丘に息づくチーズづくり。
そこには、この土地と人が紡いできた香り高い文化があった。 
- 信州東御市は、“日本のブルゴーニュ”とも呼ばれる。
昼夜の気温差は9〜10度、夏と冬の寒暖差は40度以上。長野県のなかでも小雨地域で、清らかで澄んだ冷涼な空気は乾燥している。ワインやチーズなど発酵食品づくりには理想的な環境だ。
チーズ工房とレストランが併設された「アトリエ・ド・フロマージュ」は、その東御の丘、浅間山の南斜面、標高900メートルの地点にある。
1982年、出版界から転身した松岡茂夫・容子夫妻が「日本でも本格的なカマンベールを」という夢を抱き、フランスで学んだ技術を持ち帰って開いたチーズ工房。当時の日本ではナチュラルチーズはほとんど知られておらず、生産者も稀な時代だった。松岡夫妻は、この地で未来を見つめ、挑戦を始めた。
その志を受け継き、製造と熟成の責任を担うのは塩川和史さん(写真)。地元・東御の出身で、工房からほど近い場所で育ち、チーズづくりに携わって17年になる。 
生乳の良さを最大限に活かすこと
- 「この土地の魅力は、まず空気がきれいであること。そして発酵・熟成の仕事ですから、余計な菌の繁殖を抑えるには、空気は乾燥しているほうがいいですね」
温暖化のせいか、ここ数年、夏は30℃を超える日が増えたそうだが、夜になると山から吹き下ろす風で20〜23℃まで下がるのだとか。
「牛は寒さには強いのですが暑さには弱く、極端な高温では乳脂肪が落ちてチーズがどうしても淡泊になってしまうんです。でもここでは、昼は暑くても、夜の涼風が牛を休ませ、乳質を回復させてくれます」
安定感のあるホルスタイン、濃厚なジャージー、ブラウンスイス──近隣から搾りたての生乳が毎朝届く。
「チーズづくりは、生乳に寄り添い、その良さを最大限に活かすことです」
かつてはフランス式でつくり、仕込みのマニュアルもつくってきた。でも思うような結果は出ない。それなら、「自分の感覚でやるしかない」──そう心に決め、試行錯誤を重ねてきた。 
湯の丸高原の軟水で育つ
- 生乳の質は、日毎微妙に異なる。チーズづくりは「この乳なら、こう変化していくだろう」という、その日の生乳の声に耳を澄ませながらの積み重ねだ。仕込み方は毎回違う。
「たとえば同じチーズでも、東御で熟成させれば花のような香り。湿度の高い軽井沢で熟成させれば古漬けのような風味。どちらがいいかではなく、環境が違えば、別物になるということですね」
香りと味わいを高いレベルで安定させて生み出すには、磨かれた〝未来を見通す力〞が必要なのだ。
そして塩川さんは「水」についても話してくれた。
「水はとても大切です。湯の丸高原から流れる清らかな水は軟水で、この水が草を育て、牛が飲み、やがて乳となって、チーズに姿を変えます」
ヨーロッパはほとんど硬水。チーズづくりの本場・フランスも硬水だ。硬水はカルシウムを多く含み、チーズに力強いミネラル感を与える。一方、軟水はチーズにやわらかな味わいを与え、まろやかな余韻に導く。
努力と経験に裏打ちされた人間の感覚、偶然とも思える揃った環境から生み出されたのは、日本初のフロマージュ・フレをはじめ、カマンベールやカマンブルー、ウォッシュやセミハードなどへと広がり20種を超える。塩川さん傑作のブルーチーズ「翡翠」は、世界的なコンテスト「ワールド チーズ アワード」でベスト16に輝き、国際的評価を受けた。 
- 「森のチーズレストラン」のランチで、生ハムやオリーブとともに楽しめる「森のチーズプレート」を注文した。
フロマージュ・フレは、爽やかな酸味とミルクの甘みが軽やかでフレッシュ。クリーミーなカマンベールは、角がなくやわらかい。塩味は感じるのに、舌に残るのはやさしいまろやかさだ。ブルーチーズは、シャープな塩味とそれを包み込む熟成した生乳のコク。燻製された硬質タイプは、香ばしい薫香が鼻をくすぐり、歯ごたえがありながらもなめらか。噛むほどに旨みが広がる。ワインが欲しい……あ、車で来たのだった。ならば、ショップから自宅へ送るとするか。
「アトリエ・ド・フロマージュ」がここにできてから、今日まで一日たりとも同じ気候の日はなく同じ質の生乳は、きっとなかった。まろやかで調和のとれた味わいを持つ宝石のようなチーズたちは、まさにこの土地と人の力から生まれた“ワンオフ”のようなものなのだ。
アトリエ・ド・フロマージュ Atelier de Fromage
森のチーズテラス レストラン
- 住所:長野県東御市新張504-6 0268-71-6174
TEL:0268-71-6174
営業時間:10:00~17:30(お食事14:00 L.O.)(デザート・ドリンク17:00 L.O.)
定休日:木曜日
アクセス:上信越自動車道〈東部湯の丸IC〉から車で約10分
www.a-fromage.co.jp 
勢登家 SETOYA
旧北國街道の宿場町に芽吹いた、醤油づくりの文化
- 上田からほど近い、旧北國街道・柳町に残る古い町家。
そこから発信されているのは、「醤油をつくる文化」。
発酵の香りが満ちる工房とカフェへようこそ。 
- 上田駅から徒歩15分ほど。旧北国街道・柳町は、江戸時代の宿場町の面影が残る。かつては旅籠や商家が軒を連ね、街道には柳の木が立ち並んでいたから「柳町」。白い土塀に格子戸の家、古道具店、杉玉を掲げる造り酒屋──いまも往時を偲ばせる町並みに、地酒やそば、スイーツなど地元の味を扱う店が集まり、上田城下の商い処としてにぎわっている。
その一角に掲げられた「勢登家 SETOYA」の看板は、街道を入るとすぐに見つかる。古い町家を改装した建物は、右手に醤油工房、奥にカフェ&バルを備え、発酵文化を体感できる場になっている。
「『勢登家』という名前は、この建物がかつて質屋として営まれていた頃の屋号をそのまま引き継いだものなんです」
「醤油をつくるのではなく、醤油づくりの文化をつくりたい」
- オーナーの水谷淳二さんは三重県出身。居酒屋の店長として数年勤め、アイルランドに留学、前後して農業を学び、京都で出会った醤油の搾り師から文化継承の大切さを教わった。
「『身土不二(しんどふじ)』という言葉があるんです。体と土地は二つにあらず。その土地のものを使った食事をしたり、建物を建てたりすることで、快適に健康に暮らせる──そんな考え方です。帰国後、日本の文化を発信していきたいと強く思いました」
「醤油をつくる」こと自体ではなく、「醤油をつくる文化」をこの町に根づかせたい──その思いが活動の出発点だった。
2013年からは上田で醤油づくりのワークショップを始めた。 
1日を通して楽しめる「発酵カフェ&バル」
- 仕込みは一年がかり。大豆と小麦を蒸し、麹を合わせ、もろみを仕込む。やがて琥珀色へと変わっていく過程は、菌との静かな対話でもある。
「菌は見えない、でも変化は見える。菌との会話を実感してほしいんです」と水谷さん。
顕微鏡でしか見えない世界が、時間をかけて目に見える変化を遂げることに、一種のロマンを感じるという。
水谷さんが目指すのは、地域に開かれた“公民館”のような存在だ。仕込みや搾りを地域の人とともに行うワークショップは、当初1組から始まり、10年で10組以上に広がった。1組が5〜6家族というから、参加者はすでに何百人にものぼる。ひと樽に仕込んだ醤油は一升瓶で30本ほど。それを1年後に分け合う。水谷さんは、かつてさまざまな土地で営まれていた手づくり醤油の文化を現代に蘇らせているのだ。 
- 工房の奥に広がるカフェ&バルでは、自家製醤油を使ったランチやモーニングのほか、パンやスイーツ、発酵ブレンドコーヒーや信州産ワイン・クラフトビールなど、1日を通して楽しめる。毎週水曜と土曜には、妻・未来さんが営む「日なた堂ベーカリー」も店内に開かれ、焼きたてのパンの香りが発酵の空気に重なる。
「人間はある程度、自分の都合で何とかできる。でも醤油は、自然の法則に従わなければ完成しない。菌や環境に寄り添って、ようやくかたちになるんです。それを分かち合いたい」
だからこそここは、単なる醤油屋ではなく、発酵を通じて人と人、人と自然がつながる場なのだ。柳町の歴史に新しい風を吹き込みながら、「勢登家」は、信州発酵文化圏の“交差点”として広がりを見せている。
勢登家 SETOYA
- 住所:長野県上田市中央4-7-36
TEL:090-5558-4044
営業時間:平日 10:00〜22:00 L.O.21:30
土曜日8:00〜22:00(L.O.21:30)
日曜日8:00〜17:00(L.O.16:30)
定休日:火曜日・金曜日
アクセス:JR「上田駅」から徒歩約15分
www.instagram.com/setoya.yanagimachi/ 
- 今回の取材先はいかがでしたか?
信州・長野での旅行を楽しんでいただけることを願っています。
comforts.jpは、東急ホテルズが運営する、旅行好きの皆様に向けたウェブメディアです。
日本の魅力的な観光地やその土地の美味しいグルメ、文化や最新のトレンドなど、好奇心を刺激する旅行情報を厳選してお届けしています。
さらに、ホテルでの過ごし方や周辺の散策スポットなど、旅をより豊かにするヒントも多数ご紹介。
旅行へのワクワク感を高め、思い出を輝かせるパートナーであるために、comforts.jpは、もっと楽しく過ごせる、多彩な旅行情報をお届けします。